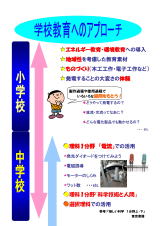|
活 動 内 容 |
 |
自転車発電、手力ためる君、ぴかちゅう(光無線通信 with 懐中電灯)、色の三原色等いろいろ教材の作製及び実践を行っています。(詳細は今しばらく、お待ちください。)
また、「理科工作クラブ」も立ち上げ、学部内の大学生と一緒にも行っています。ぜひ、興味のある大学生(現時点では山口大学・島根大学の学生に限る)はご連絡ください(事業タイトル「教員を目指す大学生のための教材開発・実践サークルにおける体験活動」)。教育関係者の方には開発支援・技術支援も行いますので、お気軽にご連絡ください。 |
| 自転車のハブダイナモを用いた手回し発電機を制作しました。DC12Vの小型テレビが見えるぐらいの発電が可能となりました。詳細は後日掲載します。2009/1/21
|
|
|
コンデンカー
(コンデンサーミニ四駆) |
| 市販電池ではなく、コンデンサーに貯めた電気によって走るミニ四駆です。教育現場には必ずある(はず)手回し発電機を用いて蓄電を行います。コンデンサーと充電池の放電の違いを示すために蓄電池で走るミニ四駆も製作しました。以下で示す「手力ためる君」と同じく、「エネルギー生成・変換・備蓄」をテーマとした教材です。 |
作業風景及び
部品 |
   |
| コン電カー |
   |
| 準備物 |
○ミニ四駆 ○コンデンサー 2.5V, 10F 2個
○ダイオード 2個 ○スイッチ
○その他、いろいろ |
|
温度差発電
(ペルチェ素子) |
| ペルチェ素子を活用した温度差発電です。構造は簡単でペルチェ素子の両面に銅板を取り付け下写真のように折り曲げると完成です。高熱源と低熱減源にそれぞれ接触させることにより発電します。太陽光モーターを用いて発電の確認を行います。 |
作業風景及び
部品 |
   |
温度差発電の
様子 |
  |
| 準備物 |
○ペルチェ素子 ○太陽光モーター&プロペラ
○銅板
○熱伝導両面テープ |
|
| 手力ためる君 |
エネルギー変換教材です。多くの場合は運動エネルギーを電気エネルギーに変え、そのまま活用しますが、こちらは備蓄(充電)も備えています(エネルギー生成、変換、備蓄)。3台の試作のもと、現在の「手力ためる君」になりました。自分の力で作った電気を貯め、それをおもちゃで遊ぶという流れです。市販の手回し発動機とこの手力ためる君があれば、いくらでも充電池に電気を貯めることが可能です。どこの科学教室、小中高等学校で行っても大好評です。
(簡単には手回し発動機で発電した電気を充電池に充電する教材です。) |
■理解すること■(小中高等学校全てに対応可能です。)
○エネルギー生成、変換、備蓄 ○電気を作る大変さ体験
○LEDの性質理解。 ○整流回路理解
○フレミングの左手の法則 その他いろいろあります。 |
| 手力ためる君 |
 (外観) (外観)  (内側回路) (内側回路) |
|
(手回し発動機をつなげるだけです。電圧計・電流計をつなぐことが可能であり、定量的議論も可能です) |
手力ためる君II
(内部回路理解のためのキットも製作しました。
|
  |
| 実践の様子です。充電した電池でたとえば馬のおもちゃを走らせています。 |
  
  
|
| 準備物 |
お問合わせください。
「エネルギー生成・変換・備蓄をテーマとした教材開発と実践」 重松他
日本エネルギー環境教育学会第二回全国大会 2007年8月7日(火)(8/7(火)- 8/8(水)) 高知工科大学にて発表 |
|
| 教材用小型風力発電 |
| 小学生対象に風力発電のシステムを理解するための教材です。こちらは既に多くの方により、公開されているものではありますが、輝度の高いかつ8mmLEDを用いたりと児童が興味が持てる構成にしています。組み立て、色塗りは児童に行ってもらいますが土台(木材・塩ビパイプ加工)作製は大学生により事前に準備します。大学生に対する工作技術(糸のこ盤、やすりがけ、くぎ打ち、半田付け等)の向上も目的に入っています。 |
大学生による
事前作業風景
|
   |
| 準備物 |
○直径14mmの丸棒、高さ150~180mmにカット
○平板、お好みのサイズで可 ○塩ビパイプ VPM16、60mm程度にカット
○マブチモーター 12Vまたは24Vのもの
○LED 8mm赤 ○モーター用羽
○PPシート比翼用、100円ショップで購入)
○釘 ○木工用ボンド |
|
| 自転車発電 |
言わずと知れた「自転車発電」。力学的エネルギーから電気エネルギーへの変換を学びます。整流回路を用いた交流から直流への整流の仕方をオシロスコープを用いて学習します。
小学生から高校生までの幅広い活用が可能です。 |
| 製作風景 |
  |
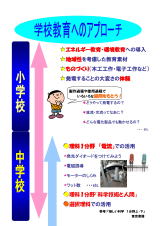  |
実践の様子
|
  |
  |
| 準備物 |
以下の文献をご参照ください。
「サイエンスEネットの親子でできる科学工作2」川村康文編著 かもがわ出版
ISBN 4-87699-584-2 |
|
太陽光発電
システム |
| 重松准教授の指導のもと、教育現場で活用できる太陽光発電システムを製作しました(「理科工作クラブ」)。計画から完成まで数か月を要しましたが、学生は①:太陽光発電の原理・システム理解、②:工作技術向上がなされたことと思います。現在、固定用パネル(140
W)により、発電された電気は物理学実験室において活用されています。移動用パネル(18 W)は出前講義用に活用されています(エネルギー環境教育として用いています)。 2008月5月17日(土)完成 |
| 太陽光パネルとコントロールシステム |
  |
| 蓄電、コントロール部全体 |
 |
太陽光パネル(シャープ、NE-70A1T、70W 2枚)
コントローラー(未来舎、PV-1212D1A)
バッテリー(LONG、完全密封型鉛蓄電池 (12V 28Ah) 、6台)
DC/ACインバーター (500 W用)
電流計&電圧計
発電量及び消費電力管理用パソコン&モニター |
|
| 蛍光灯発電 |
| エネルギー環境教育の一環として、小型太陽光パネル、充電池、CdSセルにより構成された蛍光灯による発電教材を作製しました。廊下上部に設置し、廊下の電気が消えた時に感知し、LEDが付くようになっています。 |
(左)通常
(中)夜間・廊下の電気消灯時
(右)蛍光灯上部に小型太陽光パネル |
   |
|

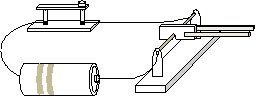






















 (外観)
(外観)  (内側回路)
(内側回路)